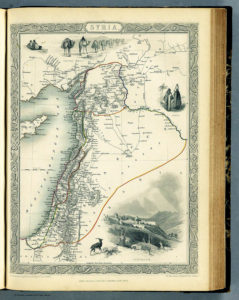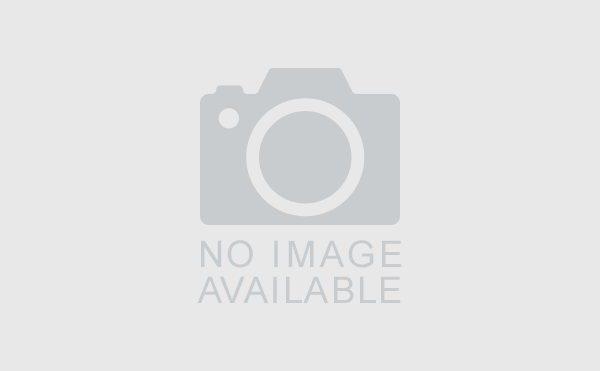3.11に思うこと 2018年3月4日
3.11に思うこと
ラジオ関西オンエア
(社)神戸国際支縁機構
理事長 岩村 義雄
完全原稿 ⇒ 3.11に思うこと
3.11から7年を経て,最大の被災面積である宮城県石巻市にほぼ毎月のように神戸から行かせていただいています。何もたいしたことができていません。83回神戸からボランティアに訪問している渡波(わたのは)地区にある長浜幼稚園(宮城県石巻市)で3月2日,園児たちと餅つき大会をしました。
7年前,大地震から約半時間経ると津波が押し寄せるなどだれも考えていませんでした。まだ首がすわっていない乳児をおんぶして「てんでんこ」に逃げるしかなかった母親,赤ちゃんにミルクを飲ませる哺乳瓶を消毒したくても,ライフラインがありません。紙オムツもなく,おしめを洗うこともできず,道の水たまりですすぐしかなかった震災後の日々。家が流され,家族を失ったり,友や仕事場の同僚もいなくなった恐怖の体験でお乳も出なくなり,自分の乳飲み子のためご近所に授乳を頼みに探し回ったことなど,昨日体験したことのように幼稚園の収穫祭で,同じ震災を体験した神戸のボランティアに話してくださいました。
そうしたサバイバルで育った子どもが3月14日に卒園します。卒園前に園児たちがどうしてもやりたかった餅つき大会です。

後藤竜記園長 2017年5月23日
年長組の園児たちと一年にわたり,交友しました。田植えのトロトロ層づくりで出会った時は,みんなは例年の園児たちより一回り幼く見えました。
3.11の震災の時,乳児だったり,胎内,まだ生まれていなかった赤ちゃんは厳しい状況におかれていました。5才になり,野外で会う度に成長していきました。かえるや虫がこわく,触れなかった子ども達も田植えの時,すっかり野外に溶け込みました。足で踏んでトロトロ層をつくり,田植えをした稲穂が大きくなり,機械を使わずに,手で稲刈りをしました。
「稲架掛け」(はさかけ)により,天日干しのおいしい米づくりに挑戦しました。稲刈りから1ヶ月,どこよりもおいしい無農薬,有機の「ヒトメボレ」を自分たちで作る喜びが芽生えました。ネオニコチノイド系農薬を使っていない苗は隣りの大崎市のNPO田んぼの千葉富男理事から毎年購入しています。化学肥料を用いずに栽培する農法は神戸の兵庫農漁村社会研究所保田茂所長が2012年7月28日以降,農法,保田ぼかし(無農薬,有機による乳酸菌こやし)を機構の若者たちに教えて下さっています。「耕支縁」(神戸市西区友清 自産自消 「自分で作って,自分で食べる(消費する」2013年10月1日以降)を「Let’s 農林漁」の講座に平行してはじめました。炊き出し(東遊園地[神戸市役所隣] 2014年4月17日以降)の野菜として役立っています。園児たちも大正時代の稲こき機を用いて,脱穀の方法に取り組みました。
脱穀
収穫祭では,じぶんたちがつくったお米でおにぎりを食べてとてもおいしかったこと,身体全身で味わいました。一年を通じて,瑞穂の国の米がどうやって食卓のごはんになるか学びました。
父兄や地元の人たちに年長組は元気よく手話を交えた演技を発表。1年でこんなに成長した陰には後藤竜記園長をはじめ多くの教師達のひたむきな教育者としての献身的な情熱と使命感がありました。とりわけ奥津めぐみ教頭は「縁の下のちからもち」,また地元の遠藤とく子さんたちもご協力くださいました。
卒園式間近に父兄や地元の人たちに年長組は元気よく手話を交えた演技を発表。1年でこんなに成長した陰には後藤竜記園長をはじめ多くの教師達のひたむきな教育者としての献身的な情熱と使命感があったことが伝わります。
朝,雪でしたが,晴れ渡りました。寒風もなんのその,「ぺったん,ぺったん」と大きな掛け声が渡波に響き渡りました。臼,杵は修空館道場からご好意で毎年,お借りしています。
餅つき大会は卒園式の2週間前。コアラ組やパンダ組の皆さん一人ひとりが心のこもった絵手紙を綴って,神戸国際支援機構にプレゼントしてくださいました。思いがけないサプライズに感動します。卒園すると,幼稚園の先生方も寂しくなる気持ちが痛いほどわかります。小学校に行きますから,餅つき大会の日で,神戸のボランティアと園児は最後のお別れです。
園児たちと築いた「縁」は虹のようにいつまでも良い思い出になり,学校生活,思春期,受験など困難にぶつかるとき,田植え,稲刈り,脱穀などの体験が活かされることを願います。

卒園する41園児からの絵手紙 2018年3月2日